金利とは?種類や計算方法、注意点などをわかりやすく解説
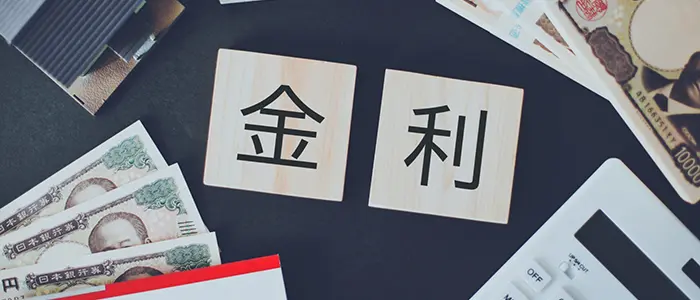
お金を預けたり借りたりする際に気になるのが金利ではないでしょうか。金利は個人の日常生活だけでなく、企業活動や国の経済にも影響を及ぼします。
金利の難しいところは、表示されている数字だけを見て「良い」「悪い」を判断することができない点です。
同じ金額を預けても、金利の種類によっても将来受け取れる金額に差が生じます。そのため、金利の定義や種類、具体的な計算方法などを知ることは大切です。
ぜひこの記事を確認し、今後の参考にしてください。
金利とは?簡単に言うと利息・利子の割合
金利とは、お金を貸したり借りたりする際に生じる利息や利子の割合のことです。
例えば、銀行にお金を預けると、預けた金額に対して「利子」が付きます。反対に、銀行からお金を借りると、借り手は銀行に対して「利息」を払わなければなりません。金利は、この上乗せされる対価の割合のことを指し、パーセンテージで表します。
具体的には、貸し手が金利年5%で1万円を貸した場合、借り手は1万円に対して5%の金利を支払う必要があるため、返済時期が1年後であれば500円分の利息を上乗せし、1万500円を返済しなければなりません。
金利には、以下の3つのパターンがあります。
- お金を預けた場合の金利
- 投資した場合の金利
- お金を借りた場合の金利
それぞれについて詳しく解説します。
関連記事:金利と利子の違いはなに?他にも違いを知っておきたい用語を紹介
お金を預けた場合の金利
銀行などの金融機関にお金を預けると、預金者は銀行にお金を貸すことになるため、金融機関から預金の残高に応じて利子を受け取ることになります。
銀行預金の金利は預金の種類や銀行によって異なります。預ける期間が同じ場合、金利が高いほど利子の額が増えるため、よく比較検討することが大切です。
預貯金の金利は債券などの投資商品の金利などと比較すると低い傾向があるため、将来受け取れる利子の額は少額ですが、元本が保証され安全性が高い点がメリットといえます。
投資した場合の金利
債券を購入すると、債券の発行者である国や地方自治体、企業などへお金を貸すことになります。そのため、その額面金額に応じて利子を受け取ることになります。
ただし、銀行預金とは異なり元本は保証されていません。債券の保有者に額面金額が払い戻される償還日を待たずに売却すると、場合によっては投資元本を下回ることがあります。
このように、債券は売却のタイミングによって損をしたり利益が得られたりといった特徴がありますが、債券の保有期間中は定期的に利子を受け取れ、償還日を待てば元本が手元に戻ってきます。
お金を借りた場合の金利
各種ローンで金融機関からお金を借りる場合、借入金額と金利に応じた利息を支払わなければなりません。
ローンは目的別にさまざまな種類があり、代表的なローンとしては住宅ローン、教育ローン、マイカーローンなどがあります。金利はローンの種類や金融機関によって異なります。
借入金額や金利が低いほど支払う利息の総額が少なくなるため、借入れの際は念入りにシミュレーションすることが大切です。
金利はどう決まるのか
お金を預けたり借りたりする際、金融機関が定める預金金利や貸出金利の元となる金利のことを「政策金利」といい、政策金利は各国の中央銀行によって決められます。日本では日本銀行が政策金利を決定しています。
政策金利は国の景気をコントロールする手段として利用されており、景気が良い局面では金利を引き上げます。金利が高くなると企業や個人は金融機関からお金を借りづらくなるため、経済活動が抑制されて景気の過熱を防ぐことができるとされています。これに伴い、物価を押し下げる圧力が働くようになることが期待されます。
反対に、景気が低迷している局面では政策金利を引き下げ、資金調達のハードルが下がるように調整します。金利が下がることによって企業は資金調達しやすくなり、経済活動が活性化し、景気を上向かせる方向に作用します。
金利の種類
金融商品には、単利で利子を計算する商品と複利で計算する商品があるため、金利は「単利」と「複利」の2種類があります。
両者の違いについてさらに詳しく解説します。
単利型
単利とは、元本に対してのみ利子が発生する計算方法です。
具体的には、元本50万円を単利2%で3年間運用すると、毎年得られる利子は50万円×2%=1万円で、3年間の利子の総額は1万円×3年=3万円となります。元本と合わせた合計金額は53万円になります。
(※税金は考慮しないものとします。以降の計算においても同様です。)
このように、単利は利子を元本に組み入れて再投資せず、元本のみに利子が付きます。
複利型
複利とは、利子を元本に組み入れ、その額を次の期の元本として利子を計算していく方法です。運用期間が長ければ長いほど、単利よりも複利のほうが利子の総額が多くなります。
具体的には、元本50万円を複利2%で3年間運用すると、初年度の利子は50万円×2%=1万円で単利と変わりません。しかし、2年目の元本は51万円になるため、利子は51万円×2%=1万200円となり、合計金額は52万200円になります。3年間運用すると、元利合計金額は53万604円となり、単利で運用するよりも大きな額が得られることがわかります。
金利の計算方法
単利は、「元本×金利」の計算式で表され、複利は「(元本+利子)×金利」で計算します。複利は利子を元本に組み入れていくため、単利と比較すると計算がやや複雑です。
大切なお金を同じ期間預けるなら、できるだけ多くの利子を受け取りたいものです。投資を始める前に、単利と複利の計算方法の違いを理解し、自分で計算できるようにしておきましょう。
金融機関に預入額を提示したうえでシミュレーションしてもらうのも良い方法です。
100万円の年利2%はいくら?
100万円を10年間複利で預けた場合の年利による合計金額の違いは、以下の通りです。
| 運用期間(年) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年利(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1,010,000 | 1,020,100 | 1,030,301 | 1,040,604 | 1,051,010 | 1,061,520 | 1,072,135 | 1,082,857 | 1,093,685 | 1,104,622 |
| 2 | 1,020,000 | 1,040,400 | 1,061,208 | 1,082,432 | 1,104,081 | 1,126,162 | 1,148,686 | 1,171,659 | 1,195,093 | 1,218,994 |
| 3 | 1,030,000 | 1,060,900 | 1,092,727 | 1,125,509 | 1,159,274 | 1,194,052 | 1,229,874 | 1,266,770 | 1,304,773 | 1,343,916 |
| 4 | 1,040,000 | 1,081,600 | 1,124,864 | 1,169,859 | 1,216,653 | 1,265,319 | 1,315,932 | 1,368,569 | 1,423,312 | 1,480,244 |
| 5 | 1,050,000 | 1,102,500 | 1,157,625 | 1,215,506 | 1,276,282 | 1,340,096 | 1,407,100 | 1,477,455 | 1,551,328 | 1,628,895 |
例えば100万円を年利2%で10年間預けた場合、1,218,994円となります。
運用期間が長ければ長いほど、年利が高ければ高いほど、将来受け取れる金額が大きくなることがわかります。
金利は高いほうがいい?低いほうがいい?
金利の高い低いは、立場や状況によってどちらが良いか異なります。
金融機関にお金を預ける際は、金利が高いほうが将来受け取れる金額が大きくなります。借金やローンを組む際は、できるだけ金利の低い借入先を選んだほうが返済額が少なくて済むでしょう。
経済全体から金利について考えると、金利が高いと企業は借入れによって十分な資金調達ができないため、経済が抑制され景気が低迷するリスクが高まります。反対に、金利が低いと資金調達が容易になり、経済の活性化につながっていきます。
また、個人消費の面から見ると、高金利は企業の業績を圧迫し、賃上げを抑制するため、消費の低迷を招く可能性があります。一方、低金利は企業の業績を後押しし、賃上げを通じて個人消費を活性化させる効果を期待できます。
金利とはお金の貸し借りで生じる利息・利子の割合
金利とは、お金を貸したり借りたりする際に生じる利息や利子の割合のことです。
金融商品の利子の付き方には、単利と複利の2種類があります。単利は初めに預けた元本に対して利子が付きますが、複利は元本に利子を組み入れて計算するため、同じ金額を預けても将来的に受け取れる金額に差が生じます。
同じ金額を同じ期間、同じ年利で預ける場合、単利より複利のほうが合計金額が大きくなることを理解しておきましょう。
金利は金融機関や商品によって異なるため、よく比較検討したうえで決めることが大切です。
2025年4月30日現在