【2022年度最新版】リフォーム・リノベーションの補助金制度をFPが徹底解説!

住宅のリフォームには優遇制度があることをご存知ですか?「おトクな制度があれば使いたいけれど、よく分からない…」という方も多いのではないでしょうか。
優遇制度のなかには「補助金」と「減税」に関するものがありますが、今回は補助金制度について解説したいと思います。せっかくリフォームするのであれば、補助となる対象工事や申請期間などをしっかり押さえておきましょう。
リフォーム減税について気になる方は、「【2023年最新版】リフォーム減税の制度を税理士が徹底解説!」をご覧ください。
2022年度のリフォーム補助金制度の解説
2022年度の主なリフォーム補助金制度は、下記になります。
- ※当記事は2022年12月12日現在の制度に基づき作成しております。
- 介護リフォームの費用を補助する介護保険の補助金制度
- 地方自治体の介護リフォーム補助事業
- 既存住宅における断熱リフォーム支援事業
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業
- こどもみらい住宅支援事業(2022年度受付終了)
- 次世代省エネ建材の実証支援事業(令和4年度受付終了)
それぞれの補助金制度の申請期間や対象工事、補助金の交付額などについて詳しく説明していきます。
- ※2021年に実施されていた「グリーン住宅ポイント制度」は申請受付を終了しており、2022年12月現在において、今後の実施に関する発表はされていません。
介護保険の補助金制度
介護保険の補助金制度は手すりの設置など要介護者等が安全に生活するための住宅改修費用を補助することを目的とした制度です。
対象となる方
介護保険の補助金制度の対象となるのは以下の条件を満たした方です。
- 要介護認定されている介護保険の被保険者であること
- 対象の住宅が被保険者の住所と一致すること
- 利用者が福祉施設や病院に入っていないこと
対象となる工事
介護保険の補助金対象となる工事は、以下の6項目です。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 床材、通路面の材料変更
- 引き戸などへの扉への取替
- 洋式便座などへの便座の取替
- 上記5つの工事に付随する改修工事
補助される金額
補助金の対象になる住宅改修費は最大20万円で、介護保険自己負担割に合わせて、住宅改修費の7割~9割が支給されます。そのため、支給金は最大で18万円になります。
また、住宅改修費の支給は原則として1人あたり20万円までですが、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合、または転居した場合は、再度上限20万円までを対象とした補助金を受給できます。
地方自治体の介護リフォーム補助事業
各地方自治体が独自で補助事業を実施している場合があります。介護保険による補助金と併用できるものや、介護認定されていなくても利用できるものなど、様々な補助制度があります。詳しくは自治体の窓口や担当のケアマネージャーに相談してください。
今回は例として、千葉県千葉市が行っている「高齢者住宅改修費支援サービス事業」の内容を見ていきます。
対象となる方
高齢者住宅改修費支援サービス事業の対象となるのは、千葉市内に在住の65歳以上の要介護(要支援)認定者です。
- ※身体障害者手帳(1級・2級)、療育手帳(AからAの2)をお持ちの方、世帯員に一定以上の収入がある方は当事業の対象外となります。
対象となる工事
対象となる工事は以下の通りです。
- 浴室
- 洗面所
- 便所
- 玄関
- 廊下
- 階段
- 台所
- 居室
- 屋外(玄関アプローチ)
- ※身体的に現に支障がある箇所の工事が対象となります。
また、集合住宅の場合は基本的に共用部分については対象外です。
補助される金額
助成額は、以下のように定められています。
【助成額=基準額 × 助成割合】
基準額について
補助の対象になる実改修費と70万円を比較して少ない方の額から、利用者負担額(介護保険の自己負担割合に応じて上限2万円~6万円)を差し引いた分が基準額になります。
なお、改修工事が介護保険制度の住宅改修費の支給対象の場合、または別の工事で介護保険制度の住宅改修費を利用されている場合は、介護保険支給対象相当分が控除されます(最高20万円)。
助成割合について
生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税状況に応じて、以下の割合が設定されます。
| 課税状況 | 助成割合 |
|---|---|
| 非課税 | 2/2 |
| ~143,000円(市内業者) | 2/3 |
| ~143,000円(市外業者) | 1/2 |
| 143,000円~213,000円(市内業者) | 1/3 |
| 143,000円~213,000円(市外業者) | 1/4 |
千葉市の高齢者住宅改修費支援サービス事業は、介護保険の補助金制度との併用が可能です。このように、地方自治体の補助金制度は介護保険と併用できる場合もあるため、詳しくはご自身のお住まいの地域で確認してください。
既存住宅における断熱リフォーム支援事業
「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」は、エネルギー消費効率の改善と低炭素化を促進させることを目的とし、高性能建材を用いた断熱改修を支援する事業です。支援方法には「トータル断熱」と「居間だけ断熱」の2種類がありますが、この記事ではトータル断熱について紹介します。
対象となる方
当事業の対象となる方は、以下に該当する方です。
- 戸建住宅・集合住宅(個別):個人の所有者または所有予定者、賃貸住宅の所有者
- 集合住宅(全体):管理組合等の代表者または賃貸住宅の所有者
対象となる工事
当事業の対象となる工事は、以下の通りです。
- ガラス・窓・断熱材
- 玄関ドア
- 家庭用蓄電システム
それぞれ対象となる条件があるため事前に確認が必要です。
補助される金額
当事業で補助される金額(補助率)と上限額は以下の通りです。
| 補助対象製品 | 補助率 | 補助金の上限額 |
|---|---|---|
| 高性能建材(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア・LED照明) | 補助対象経費の1/3以内 |
(玄関ドアは戸建て住宅・集合住宅ともに5万円/戸) |
| 家庭用蓄電システム | 20万円 | |
| 家庭用蓄熱設備 | 20万円 | |
| 熱交換型換気設備等 | 5万円 |
- ※1集合住宅(全体)においても適用となる。
- ※2補助対象戸数(A)、補助金上限額(1住戸当たり15万円)(B)、高性能建材(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア)による補助金額(C)
(A)×(B)-(C)=LED照明の上限額。ただし、1か所につき8,000円で、完了時に補助対象戸数が減少した場合は減額となることがある
長期優良住宅化リフォーム推進事業
「長期優良住宅化リフォーム推進事業」とは国土交通省が提供する、既存住宅の長寿命化や省エネ化等を目的とする事業です。リフォームや子育て世帯向けの改修に対して支援を行っています。
対象となる方
リフォーム工事の請負契約、共同事業実施規約の締結をされた方が対象です。また、国への申請手続きは主に施工業者(補助事業者)が行います。
対象となる工事
当事業の対象となる工事は、以下の通りです。
- 性能向上リフォーム工事
- 三世代同居対応改修工事(複数世帯が同居しやすい住宅を目的としたリフォーム工事)
- 子育て世帯向け改修工事(子育てしやすい環境整備のためのリフォーム工事)
- 防災性の向上、レジリエンス性の向上改修工事
なお、いずれの工事についても工事前にインスペクション(建物状況調査)を行い、それに基づく維持保全計画およびリフォームの履歴の作成が必要です。以下、それぞれの対象工事をご紹介していきます。
性能向上リフォーム工事
劣化対策や耐震性、省エネ対策等特定の性能項目を一定の基準まで向上させることを目的とした工事です。
- 省エネルギー対策(断熱サッシへの交換等)
- 耐震性(耐力壁の増設等)
- 構造躰体等の劣化対策(ユニットバスへの交換等)
- 維持管理、更新(給水、排水管の更新等)
- バリアフリー工事(手すりの設置)
- インスペクションで指摘を受けた箇所の補修工事(外壁の塗装等)
- テレワーク環境設備改修工事(部屋を仕切る間仕切壁や建具の設置等)
- 高齢期に備えた住まいへの改修工事(玄関スペースの拡大)
三世代同居対応改修工事
複数世帯が同居しやすい住宅を目的としたリフォーム工事で、以下を対象とした増設工事が対象です。
- キッチン
- 浴室
- トイレ
- 玄関
- ※リフォーム後にキッチン、浴室、トイレ、玄関のうちいずれか2つ以上が複数箇所あることが必要。
子育てしやすい環境整備のためのリフォーム工事
若者や子育て世帯が実施する子育てしやすい環境を作ることを目的としたリフォーム工事が対象です。
例としては以下のようなものが挙げられます。
- 住宅内の事故防止
- 不審者の侵入防止
- 災害への備え
防災性の向上、レジリエンス性の向上改修工事
自然災害に対する改修工事が対象です。以下のようなものが対象例といえます。
- 水害への備え
- 電力、水の確保
補助される金額
当事業で補助される金額(補助率)と上限額はリフォーム後の住宅性能で判断され、以下の通りです。
| リフォーム後の住宅性能 | 補助限度額 |
|---|---|
| 長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合 | 200万円/戸 |
| 長期優良住宅(増改築)認定を取得しないが、一定の性能向上が認められる場合 | 100万円/戸 |
対象となるリフォーム工事費の合計の1/3の額が補助されます。
- ※補助限度額は条件で変動があるため、検討する際はよく確認しましょう。
こどもみらい住宅支援事業(2022年度受付終了)
こどもみらい住宅支援事業は、国土交通省が提供する子育て支援およびカーボンニュートラルの実現を目的とした事業です。子育て世帯や若者夫婦世帯を対象とし、高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や省エネ住宅への改修等に対して補助金を支給するものです。対象者の住宅取得に伴う負担の軽減や省エネ機能のある住宅ストックの形成を主な目的としています。
- ※こどもみらい住宅支援事業は、2022年11月28日をもって、補助金申請額が予算上限に達したため、交付申請の受付を終了しております。
対象となる方
リフォーム補助の対象となるのは、以下の要件を満たした方です。
- こどもみらい住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする
- リフォームする住宅の所有者等である
対象となる工事
こどもみらい住宅支援事業の対象となる工事は以下の通りです。
| いずれか必須 | |
|---|---|
| ① | 開口部の断熱改修 |
| ② | 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 |
| ③ | エコ住宅設備の設置 |

| ①~③と併せて実施した場合のみ対象 | |
|---|---|
| ④ | 子育て対応改修 |
| ⑤ | バリアフリー改修 |
| ⑥ | 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 |
| ⑦ | 耐震改修 |
| ⑧ | リフォーム瑕疵保険等への加入 |
補助金の交付額について、①~⑥は工事内容に応じて交付額が設定されます。⑦の耐震改修は15万円/戸、⑧のリフォーム瑕疵保険等への加入は7千円/契約の交付額となります。①~⑧の合計補助額が補助金として交付されます。
- ※1申請当たり①~⑧の合計補助額が5万円未満の場合は補助申請できません。
ただし、上限補助額は下表の通りに設定されているので注意しましょう。
補助される金額
原則1戸あたり30万円が上限です。
ただし以下に当てはまる工事は図のように上限金額が引き上げられます。
- 子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事
- 工事発注者が、自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事
| 世帯の属性 | 既存住宅購入の有無 | 1戸あたりの上限補助額 |
|---|---|---|
| 子育て世帯又は若者夫婦世帯 | 既存住宅を購入し※1リフォームを行う場合※2 | 60万円 |
| 上記以外のリフォームを行う場合※3 | 45万円 | |
| その他の世帯※4 | 安心R住宅を購入※1しリフォームを行う場合※3 | 45万円 |
| 上記以外のリフォームを行う場合※3 | 30万円 |
- ※1売買契約額が100万円(税込)以上であり、かつ令和3年(2021年)11月26日以降に売買契約を締結したものに限る
- ※2自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結から3か月以内にリフォームの請負契約を締結する場合に限る
- ※3自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限る
- ※4法人を含む
参照:こどもみらい住宅支援事業
次世代省エネ建材の実証支援事業(令和4年度受付終了)
「次世代省エネ建材の実証支援事業」は、経済産業省が提供する高性能断熱材や蓄熱・調湿材等の次世代省エネ建材の効果の実証を支援する制度です。対象となるリフォームは「外張り断熱」、「内張り断熱」、「窓断熱」の3つの中から選ぶことができますが、今回はご参考までに「外張り断熱」をご紹介します。
- ※既存住宅における断熱リフォーム支援事業は、2022年11月30日をもって、申請の受付を終了しております。
対象となる方
当事業の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
- 改修する住宅に常時居住していること
- 改修する住宅を所有していること
対象となる工事
以下の条件を満たす工事が対象となります。
- 既存戸建住宅の外気に接する外壁全てを外張り断熱工法等にて改修すること
- 住宅の外皮性能は、当事業の運営を委託されている環境共創イニシアチブが地域区分ごとに定めた基準を満たすこと
- 本事業の要件を満たした効果測定を行い、報告すること
- 本事業の補助対象には、他の国庫補助金を受けたものが含まれていないこと
補助される金額
補助金の上限額は1戸あたり300万円~400万円です。
また、補助率は補助対象経費の1/2です。
千葉県にお住まいの方に向けたリフォーム補助金
市町村によっては、独自のリフォーム支援制度を設けている自治体もあります。地域経済の活性化が主な目的で、自治体内の資源の活用や地元の施工会社に発注することを要件としている場合が少なくありません。
今回は千葉県にお住まいの方を対象としたリフォーム補助金制度についてご紹介します。
千葉県のリフォーム補助金
千葉県在住者を対象としたリフォーム補助金制度は大きく分けて、3つあります。
1つ目は各市町村が実施する助成制度で、それぞれの市町村によって制度の詳細は異なります。
2つ目は住宅金融支援機構の「リフォーム融資」です。こちらは自宅のバリアフリー化や耐震化などのリフォームを実施する際に活用できる「融資」制度になります。詳しい融資要件については住宅金融支援機構で確認しましょう。
3つ目は高齢者向け返済特例制度です。こちらは60歳以上の方が、住宅支援機構のリフォーム融資を活用してリフォームを実施する際に毎月の返済額を軽減できる制度です。元金は死亡時に一括返済となるため、事前に担保に入れた建物や土地の処分等によって相続人が返済することになります。
これらの助成制度の他にも住宅改造のために利用できる「生活福祉資金」や「高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金」などがあります。詳細については千葉県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会に確認して下さい。
各市町村のリフォーム補助金の探し方
地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイトでは地方公共団体が実施する住宅リフォーム支援制度について検索することができます。
まず下記リンクよりページを開いたら、「お住まいの市町村」もしくは「制度内容」から補助金制度を検索しましょう。「制度内容」から検索する場合でも都道府県で絞り込みをかけることが出来るので「制度内容」から検索することをおすすめします。「支援分類」と「支援方法」、「都道府県」を選択したら、検索ボタンをクリックします。すると、対象のリフォーム制度が表示されるので「実施地方公共団体」欄からお住まいの地方公共団体が記載されている制度名(事業名)を確認しましょう。制度の詳細ページには管轄の部署の電話番号が記載されているので、制度の詳細を確認する場合にはこちらにお電話するのが最もスムーズかと思われます。
リフォーム減税について気になる方は、「【2023年最新版】リフォーム減税の制度を税理士が徹底解説!」をご覧ください。
リフォームローンならちば興銀
マイホームの老朽化や家族構成の変化に伴ってリフォームを検討する方も多いのではないでしょうか。しかし、リフォームを自己資金だけで賄うことが出来ないこともあります。そんなときに検討したいのがリフォームローンです。
それでは、ちば興銀で取扱うリフォームローンの6つの特徴についてご紹介します。
- 住宅の増改築だけではなく、生活周りを快適にするシステムキッチン・バス・トイレ等の購入資金や、造園、車庫などのエクステリア資金としてもご利用可能。
- 太陽光発電やオール電化、エコ給湯などにも対応。
- お借入金額は最大2,000万円まで、お借入期間は最長15年と長期の お申込みができます。
- お申込みからご契約までWEBで完結!さらにWEB完結型の場合お借入利率から0.1%金利を割引いたします。
- 担保/保証人不要 *保証会社が必要と認めた場合等、連帯保証人が必要となる場合がございます。
- 金利上乗せ0.3%で、「ガン保障付プラン」をご選択いただけます。
ぜひご検討の上、お申込みください。

リフォームについてのその他の記事はこちら
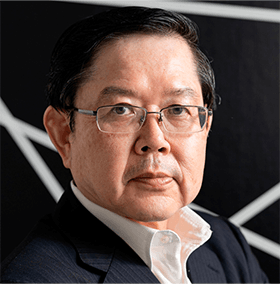
水上 克朗(みずかみ かつろう)
ファイナンシャルプランナー
慶応義塾大学卒業後、大手金融機関にて、営業・企画・総務などを経験。50代での人生の転機に、これまでの経験とFPの知識を活かし、自身のライフプランを見直し老後1憶円資産の捻出方法を確立。現在、執筆、監修、FP相談、セミナー・研修講師などで、ライフプラン、金融資産運用などの観点からアドバイスを行っており、その内容は、新聞、雑誌、Webなどの各メディアで数多く取り上げられている。著書に「50代から老後の2000万円を貯める方法」(アチーブメント出版)がある。
2023年11月1日現在


