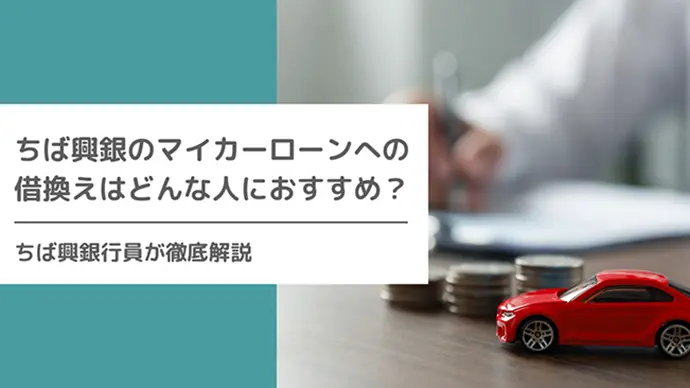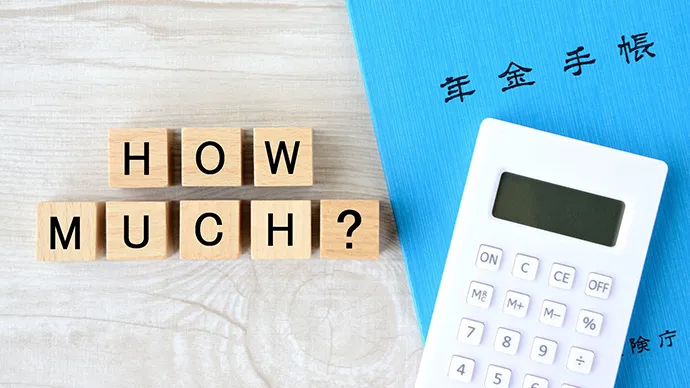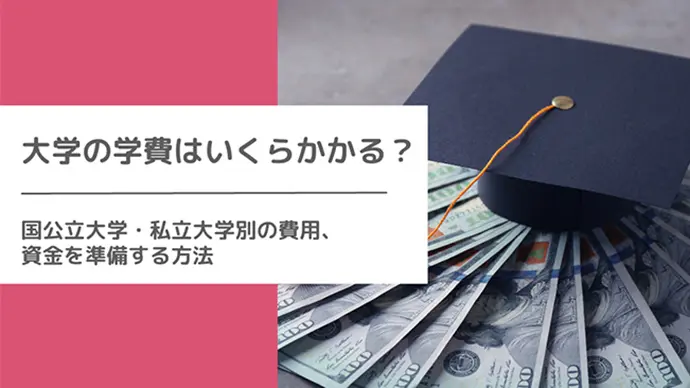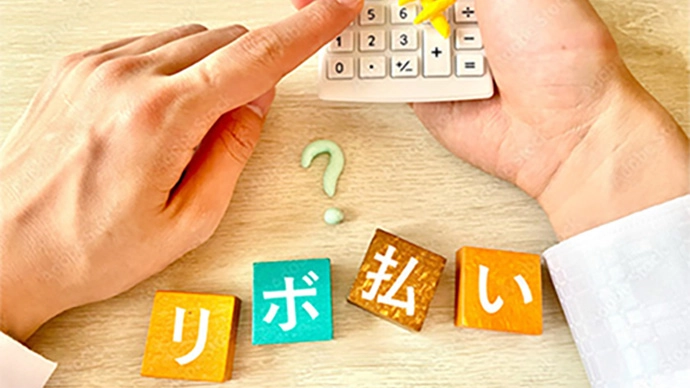事業承継から読み解くコスモスLAB.vol3:株式会社センエー(前編)
物心ついた時から家業はそこにあった。「継がない」という選択肢はなかった。

代表取締役 山本 剛 氏
| 会社概要 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社センエー |
| 代表取締役 | 山本 剛 |
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂2-12-11 |
| 設立日 | 1936年(昭和11年)4月 |
| 資本金 | 20,000千円 |
| 事業内容 | 水処理保守・清掃業務 環境保全業務 都市整備業務 総合設備工事業務 |
| HP | https://www.sen-e.co.jp/ |
「『事業承継』というフィルターを通すと多くの学びや気づきがあり、ビジネスやマネジメントがもっとオモシロクなる」がコンセプトの当企画。事業後継者育成を目的とした「ちば興銀『コスモス経営塾』」を卒業し、実際に事業承継をされた方々にインタビューを行い、さまざまな分野で活躍される経営者の体験談や経営術を発信します。経営に興味のある方、事業承継を検討されている方に、ここでしか手に入らない生きた情報をお届けいたします。
今回のゲストは、1936年(昭和11年)創業、千葉市稲毛区で千葉市を中心とした水処理施設の保守管理や環境保全業務、都市整備業務など、「水処理」に関する多岐にわたる事業を展開する株式会社センエー(以下、株式会社省略)の5代目、山本剛社長。本社を構える稲毛の地で生まれ育ち、物心ついた頃には家業を継ぐという意識があったといいます。高校生の頃からアルバイトとして家業を手伝い、大学卒業後に正社員として入社し、2014年に代表取締役の立場を引き継ぎました。
物心ついた時から家業はそこにあった。「継がない」という選択肢はなかった。

センエーの歴史は、千葉市の下水道の発展とともにある。市議会議員を務め、し尿汲み取り業を生業としていた山本政次氏が1936年に「千葉衛生舎」を創業し、戦後の近代化による下水道の本格的な普及の波に乗り、区域限定だった汲み取り業から市内全域の浄化槽清掃業へと事業を拡大していった。また、川崎製鉄千葉工場(現:JFEスチール)の誘致・開設に尽力したことで業務提携を結び、1950年の開設当初から広大な工場敷地内トイレの管理清掃業務を請け負うことになり、安定した経営基盤を築いていった。
現在、従業員数は94人、本社を含む千葉市に3カ所、市原市に1カ所、2022年には成田市にも支店を開設し、5カ所の拠点を構える。官公庁を中心とした水処理関連施設業務から民間企業の総合設備工事、保全業務など、水と設備に関する幅広い事業を展開している。
「会社とともに育ち、気づいた頃には家業を継ぐと思っていました。私にとっては、当たり前のことだったのです。」
家業に誇りを持ち、地域を愛する山本社長を育てたのは、暖かい地域の大人たちだった。
地域の人々に「誰もやらないことをやっていて偉い」と感謝された幼少時代。仕事への誇りと自信につながった。
-事業承継のキッカケを教えてください。
キッカケというキッカケはないんですよ。私は本社のあるこの地で生まれ育ったので、物心ついた頃から家業とともにあったのです。今は会社の駐車場になっていますが、当時は本社屋の横に自宅があったので、商店街の八百屋や魚屋のように、生活と家業は同じ空間でした。バキュームカーがある家なんて、うちだけでしたよ。(笑)
当社はし尿汲み取り業からスタートし、千葉市の下水道の近代化とともに事業を変化させ、成長していきました。排泄物や生活排水が流れる下水道処理がメイン事業なので、同業者の中には、幼少時代に馬鹿にされた経験があるということも耳にしますが、私は一切ありませんでした。
逆に、「みんながやらない仕事をやって偉いね」「いつもありがとうね」と近所の大人が声をかけてくれました。そんな環境で育ったので、子ども心に「うちは立派な仕事をしているんだ!」という誇りを持ち、自信へとつながっていったのだと思います。小さい頃に、トラックに乗せてもらって現場に行くこともあって、とてもワクワクしたことを覚えています。
みんなに褒められ、役に立つ仕事という認識だったので、当然大きくなったら自分が家業を継ぐものだと思っていました。私には兄がいるのですが、兄はよい大学を出て大企業に就職したので、後継者について揉めることは全くなかったですね。
高校生になると、当社でアルバイトとして働き始めて、改めて仕事の面白さを知りました。自分が工事したところに水が流れるという達成感もありますし、この業界は資格がものを言いますから、あんな工事をしてみたい、じゃあこの資格を取らなくちゃ、と、どんどんのめり込んできました。実務経験が何年か無いと取れない資格も多かったので、早く経験を積みたいとヤキモキしていました。
現会長である父は美大で工業デザインを学び、メーカーの研究所に勤めてから当社に入社したので、ユーザー視点と企業視点の両方の視野を持っていました。そのノウハウを生かして、企業名の変更や会社のロゴデザイン一新などを行い、当社の企業イメージのブランディングに成功しました。その実績があったので、私も他社で修行し広い視野の獲得をした方がよいのではと考えたこともありますが、結局大学を卒業してそのまま当社に就職しました。理由としては、当社は下水道処理事業の他にも清掃業や総合設備工事業と多岐にわたる事業を展開しており、事業ごとに必要な資格をある程度取得するには20年近くかかるため、他社で修行している時間がもったいないと感じたためです。
早くから経営にタッチ。従業員もスムーズに受け入れてくれた。

-社長に就任されたのは2014年ですが、入社して何年くらいで経営に携わるようになったのですか。
入社したのが1994年なので、社長就任までは20年かかっていますが、入社して8年目の2002年に役員になり、その頃にはお金周りのことは基本的に任されていました。現会長である当時の社長は、業界団体や法人会などのさまざまな要職を務めており、対外的な仕事を多くこなしていました。そんな中で、総務部長や経理を担当していた従業員が立て続けに退職し、社内の仕組みを見直すことになり、私が担当することになりました。
それまでに現場をある程度経験し、営業としていろいろなところに出向く機会も多く、会社や業界のルールなども学んでいたので、特に社内での混乱などはなかったですね。従業員も、スムーズに受け入れてくれた印象です。
前回インタビューを受けていた社長さんは、後継者が歓迎されるのは、後継者の小さい頃を知っている場合くらいだとおっしゃってましたが、まさに私はそのパターンで、年上の従業員から「おむつしてたのにずいぶん偉くなったね」と言われました。(笑)
あまりに私が会社に馴染み過ぎていたのでしょう。小さな頃から会社とともに育って、家業は私が継ぐものだという意識が、従業員の中にも培われていたんだと思います。100人近くの従業員がいますが、目立った反発はなく、引継ぎも非常にスムーズでした。
お客様も同様で、創業間もない頃からお付き合いさせていただいている企業様なども、滞りなくご挨拶ができました。
実感として、中小企業の承継は親族でないと難しい。後継者同士のつながりが持てるコスモス経営塾は非常にありがたい存在。
-では、承継で苦労されたことは?
そうですね…私は人間関係の部分では幸いにも苦労がなかったのですが、現実的に相続税等のお金の部分は、相当の覚悟が必要でした。
例えば資本金が2000万円だとして、2000万円用意すれば会社が継げるかと言ったらとんでもない話でしょう?私の場合は、会社の資産を受け継ぐのに大借金したと言うと言葉が悪いですが、一生の覚悟を持って準備を進めて、承継しました。
企業の承継には、M&Aなどさまざまな方法がありますが、現在の税制だと親族や子ども以外が会社を継ぐというのは非常にハードルが高いと思います。血縁の無い社内の誰かに継ぐとなっても、資金の準備ができるのかという現実的な課題があります。株の譲渡や事業資産、権利などのハード面は、外部の専門家を巻き込んで現経営者としっかりと話し合い、余裕を持って計画的に承継の準備を進めた方がよいです。
-山本社長はコスモス経営塾6期生の会長を務めていらっしゃいました。経営塾は有効でしたか?
もちろん、経営や承継に関する知識を学ぶという部分でも有効でしたが、私にとっては、経営者同士のつながりが持てることが一番ありがたかったですね。
会社を継ぐ前や継いだ後は、経営や会社について一生懸命勉強するのですが、一人で勉強していても点のままなんです。インプットした知識をアウトプットする場がないと、行き詰まりを感じますし、自分の会社にどのように落とし込んでよいのかがわかりません。そんな中で、コスモス経営塾で同じような境遇の仲間と出会い、勉強会の後に、「ここわからないよね。」「わからない。難しいよね~。」「わかった顔してたじゃん。」なんて、自然と反省会になるんです。(笑)
そこで、今日学んだことをどのように生かせるかアドバイスをしあったりしているうちに、自然とお互いの事業について話し合い、実際のビジネスでもつながりが生まれることもあります。学んだ知識が点から線になる場所、そして同じ境遇の経営者仲間と出会う場所として、私にとってコスモス経営塾は非常にありがたい存在でした。
経営者は、他にも色んなところに行って学び、刺激を受けてくるので、自分が学んだことを自分の中だけで納得して、「俺はいつも勉強してるんだ」じゃしょうがないわけです。勉強したことをどうやって落とし込んでいくか、インプットされたものをアウトプットしていくのか、自分が学んだことを、周りや従業員にどれだけ波及させられるか、これも経営者の役割だと思います。

DIRECTOR:YUSUKE TOSHI(日本企画)
WRITER:CHIAKI NAKAMURA(株式会社KiU)
PHOTO:YASUO HONMA(本間組)