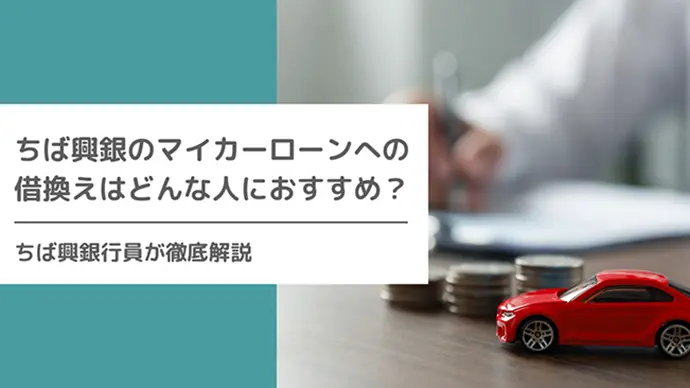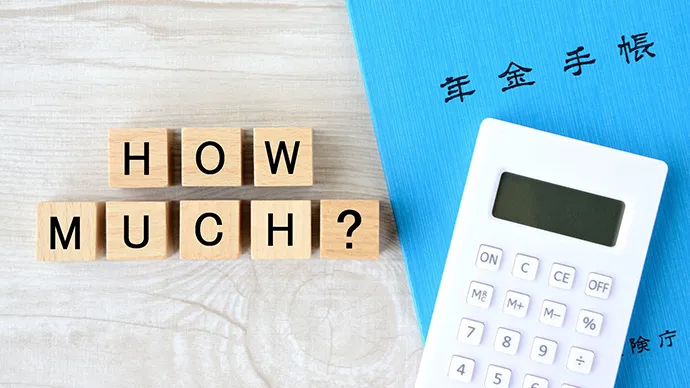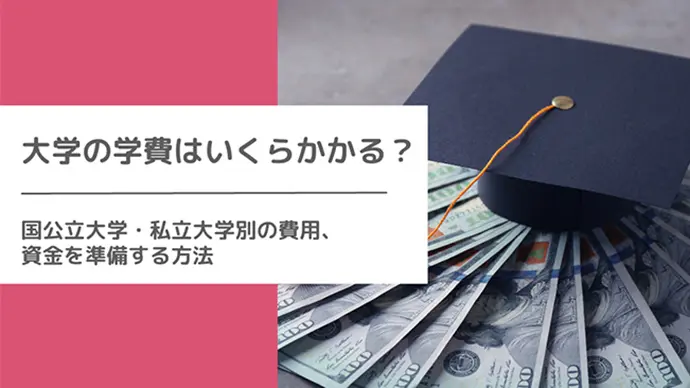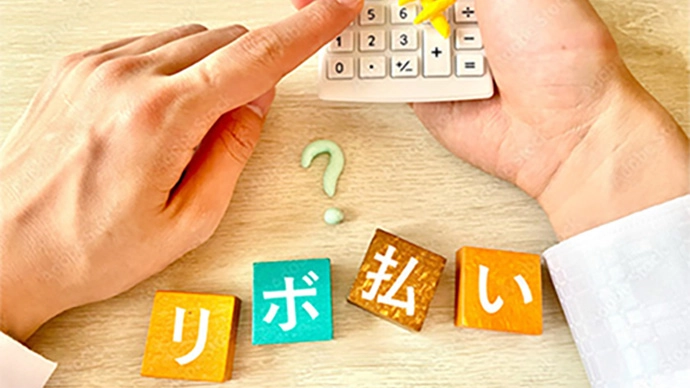企業総合診断コンサルティングのご利用事例(株式会社千葉度量衡工業所)
組織の潜在課題を可視化して 具体的な行動に繋げる
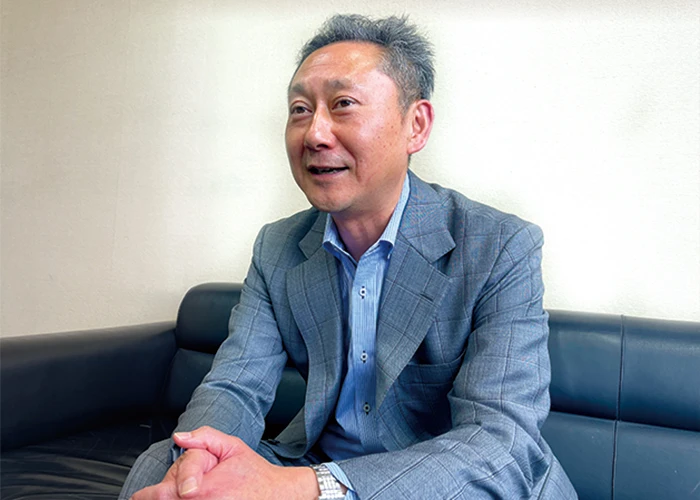
代表取締役社長 大野 真樹氏
| 会社概要 | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社 千葉度量衡工業所 |
| 代表取締役社長 | 大野 真樹 |
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区千種町49-2 |
| 設立 | 1946年6月3日 |
| 資本金 | 12,000千円 |
| 事業内容 | 自動計量装置・計量関連機器製造 |
| HP | https://www.chibado.co.jp/ |
現状の課題をあぶり出し、目的に向かって社員が動ける体制を構築できました。
株式会社千葉度量衡工業所は、千葉市花見川区に本社を構え、計量機の製造を本業としています。創業は明治時代にさかのぼり、現在の千葉度量衡工業所を戦後間もなく設立した伝統ある企業です。工業用はかりの製造を、銅板などの加工から製造、動作のプログラム、設置、アフターサービスまでを一貫して行うのが同社の強みです。米からペレットまでさまざまな製品を精確かつスピーディーに計量を実現する同社の工業用はかりは、国内のほか東南アジアでも支持されています。今後の更なる成長のために同社が選んだのは、千葉興業銀行の「企業総合診断」でした。大野真樹・代表取締役は、「モヤモヤとした経営課題を感じていたが、それが何なのか明確ではなかった」と言いますが、どのようにして企業総合診断を受けながら経営課題を明らかにしていったのでしょうか。その経緯についてお話を伺いました。
手探りだった経営 外部の方の目線で診断してほしかった。
---どのような経緯で、「企業総合診断」のコンサルティングを受けられたのですか。
代表を受け継いでから9年近くになるのですが、会社の経営全体に課題感をずっと感じておりました。ただ、その課題が具体的に何であるのか、どこから手をつけて良いのかがわからずにモヤモヤしておりました。自分たちだけで手探りで考えているよりも、外部の方に会社の中身をつぶさに見ていただいて、実際の状況など全般をみてもらいたいと思いました。
---「モヤモヤ」が募っていったということですが、
ほかに何か大きなきっかけがあったのでしょうか。
私が、先代社長である父から経営について十分に引き継ぎできなかった面もあります。父は、現役の社長だった2015年に急逝したため、私が後任の社長に就任しました。本来は時期を決めて計画的に引き継ぎを行うのが理想的なのですが、その機会もなく就任せざるを得なかったのです。
私自身は事業承継のタイミングで、経営者としてのノウハウも含めて引き継ぐつもりでいたのですがそれがかなわず、生前にもっと色々話を聞いておけばよかったなと思うことが度々ありました。父がどういう思いで経営していたかを、恥ずかしがらずに聞いておけばよかったなと。就任直後はとにかく会社を経営していくことで精一杯だったというのが実情でした。
それに、人間はいつどうなるか分かりません。自分が社長に就任してから7年が過ぎた頃に50歳を迎え、今のことだけではなくて先のことも考えなければならないと思うようになりました。父の場合は後継者の私がいたので経営を引き継げたのですが、今の状態で私に万が一、何かあったときはどうするべきか心配になりました。社員の平均年齢も40代後半になり、ここ10年ほどで定年を迎える者もおります。当社は創立78年ですが、まずは100年を目標にその先も見据えて会社経営をしっかりと進めていくために、今以上により良い企業にしたいと考え、コンサルティングをお願いしました。
---企業総合診断コンサルティングのどのような点に魅力を感じられましたか?
コストをかけてでも、自分たちだけではなく外部の専門家の視点から当社の中身をつぶさに見ていただいて、会社の実際の状況などを客観的に俯瞰したうえで課題を提示していただきたいと思いました。その方が、よりスピーディーに自分たちの目指したい組織づくりを進められると思ったからです。
部長を軸にした組織へ。
従来の「トップダウン」を刷新。
---コンサルティングはどのように進んだのでしょうか。
まずできるところから始めていきたいと思っておりましたので、コンサルタントの先生のご助言のもと、当社の組織のありかたについて従業員へのアンケートや聞き取りを行うと共に、財務分析などのデータをまとめてもらって課題を洗い出しました。この過程で、しっかりした組織として形を作っていかなければいけないということが見えてきました。
弊社には従来から組織図があったのですが、実際の組織運営とかけ離れていた部分がありました。先代の頃から、トップダウンに近いイメージで組織が動いていたのです。
そのため、どうしても最終的な結論は社長が決めてください、という文化が根付いていました。ほかにも、大きな判断に至る前のちょっとした案件でも私に直接相談してくることがあり、正しい組織としては「社長より先に、まずは現場をよく知っている部門長が判断すべきではないだろうか」と思うことも多々ありました。何かあればすぐに社長に相談するという先代の頃からの慣わしだったのですが、組織のあり方や役職者の責任を明確にしていくという姿勢を伝える必要があると分かりました。
---個別の業務においては、その部門長が深い知見を持っていると考える方が自然ですね。
そうですね。最も知見のある担当者や部署で判断できるような仕組みにすることで、より強い組織になると信じています。全体を見るのは代表の私の仕事ですが、各部署の専門的な部分は十分な知見を持っている部署の中で解決してもらい、その報告を上げてもらうような組織づくりを進めている最中です。
---具体的にはどのように、組織を変えられたのですか。組織図も書き換えられたのでしょうか。
はい、書き換えましたし、それによって社員の意識が変わってきたと感じています。部長級の者には各々が部長であることを認識し、それぞれの部署をしっかりまとめてほしいということを、月1回の部長会議も含めて徹底しています。部長の部下である従業員も、自分たちの上長は部長であるという意識が出てきていると感じます。部署および部長を軸に業務を進める組織づくりは、まだ道半ばですが浸透し始めていると感じています。
自分たちの強みを活かすために、
これまで見えていなかったことは何か。
---組織のことだけを取ってみても、ぼんやりとしていた課題感が明確になったことが感じ取れますね。

そうですね。将来に対してどういう方向に持ってくべきなのかというビジョンが、コンサルティングを受ける前と比べて明確に見えてきています。課題の一部はまさに改善を進めている最中ですが、自分が60歳の時にはこういう会社にしたいということが、見えてきました。そう考えると、人員の補充についても捉えかたが変わりました。従来は、社員の定年退職が近づいたタイミングに合わせて1年前後で人員を補充する体制だったのですが、今は従業員の年齢構成を踏まえて、先を見据えた人材採用を進めています。電気・機械設計や営業の担当者を、先を見越して早い段階から教育をしていくという考え方です。
現在の社員の平均年齢は40代後半、機械設計は50代ですので、若手育成に力を入れていきたいと考えています。たとえば入社10年に満たない者も、自分より若い人が入社してくることで後輩を育てることになり、結果として自分のスキルを上げることになりますからね。一時的にコストはかかりますが、会社を成長させて存続させていくためには、社員育成には今後も力を入れていきたいと思っています。
---結果として、各々の社員さんのモチベーションを高めることにもつながりますね。
そうですね。機械設計部門と工場の部門とで、風通しがだいぶ良くなってきた感じがありますね。以前は工場にベテラン社員が多いので、設計・営業の方が萎縮してしまうようなところがあったのですが、今は何か問題があれば部署同士、または営業担当と相談しながら対処することも増えてきました。
当社の強みの一つは、材料を購入してから製品を作るまで社内で一貫して行えるところなのですが、それだけに設計してから製造まで社内での調整が、生産スケジュールにうまく乗せる上では大事なのです。そこで、コンサルティングで頂いたアドバイスをもとに、設計時に図面をもとに部署をまたいでの会議を行っています。
「モヤモヤ」の原因を解きほぐしていくと、
他の部分も見えてくる。
---何となく感じていた課題感を少しずつ明らかにしていくと、他の課題も見えてきたのですね。
そう思います。一つの突破口が、さまざまな部分に対しても効果があるのかもしれません。
---企業総合診断コンサルティングは、コストもかかるし、社員さんの協力も必要だったと思いますが、 実施してどのような感想をお持ちですか。
会社全体を見てもらって良かったと思っています。ご指摘いただいたポイントの中にも、自分が考えていたことと合致しているなという点も結構あり、会社のありたい姿をより明確にして、その目標のもとで経営をさらに推進するうえで後押しになりました。また、社外に委託することによって、会社を本当に変えたいのだという本気度を、従業員も感じていたように思います。
最近は、お客様から製品に対するクレームよりも、お褒めの言葉をいただくことが増えました。先日もお客様が納品の立ち会いでみえた際に、「きれいに仕上げて頂いてありがとうございました」と言われました。取り組みの成果が少しずつ現れ、以前より仕事が丁寧になった感じがします。
---今後は、どういったことに取り組んでいかれるのでしょうか。
コンサルティングで助言をいただいた、攻めの営業をやっていきます。どうしても既存のお客様に偏りがちで、新規開拓が手薄になっている面がありました。そこで過去にお取引がありながら最近はお付き合いが減っている顧客に改めてご提案をしながら、丁寧に営業を進めていきたいと思っています。今後は創業100年を目標に、従業員の間の業務の継承もしっかり行うと同時に、売上を上げながら利益も今以上に出せるよう、これまで以上に成長していきたいですね。

中小企業の皆様、こんなお悩みありませんか?
- 経営課題がどこにあるか整理したい
- 客観的な分析に基づき将来を考えたい
- 具体的な改善策を知りたい
- 事業承継を踏まえて仕組みを見直したい
- 事業の方向性が絞れない
- 数値に基づき詳細な経営計画を作成したい
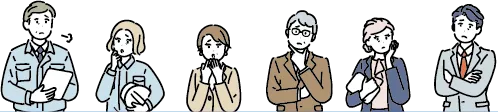
千葉興業銀行がお客様の組織づくりを
サポートします。
- 幅広い診断範囲
- 外部専門家との協力体制
- 充実した個別支援策
企業総合診断の特徴と期待される
「診断の効果」
複数の経営課題の優先順位がわかり
改善策により経営体質の強化につながる
内部環境分析(財務、事業、組織など)および外部環境分析(競合、市場など)を行い、要経営課題を抽出します。分析においては、社長や経営幹部、従業員を対象とするアンケートを行います。
“あるべき姿”実現までのプロセスが明確になり
強みの再認識により永続的な発展につながる
SWOT分析を行うほか、改善の方向性やアクションプランを提示します。今後の展望を明確にした上で、実際に踏み出すべきアクションをお示しします。